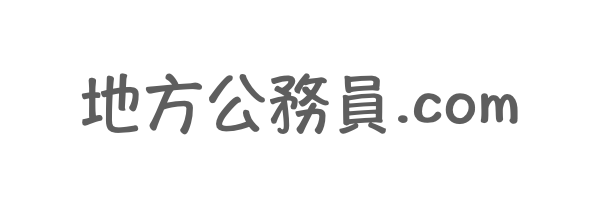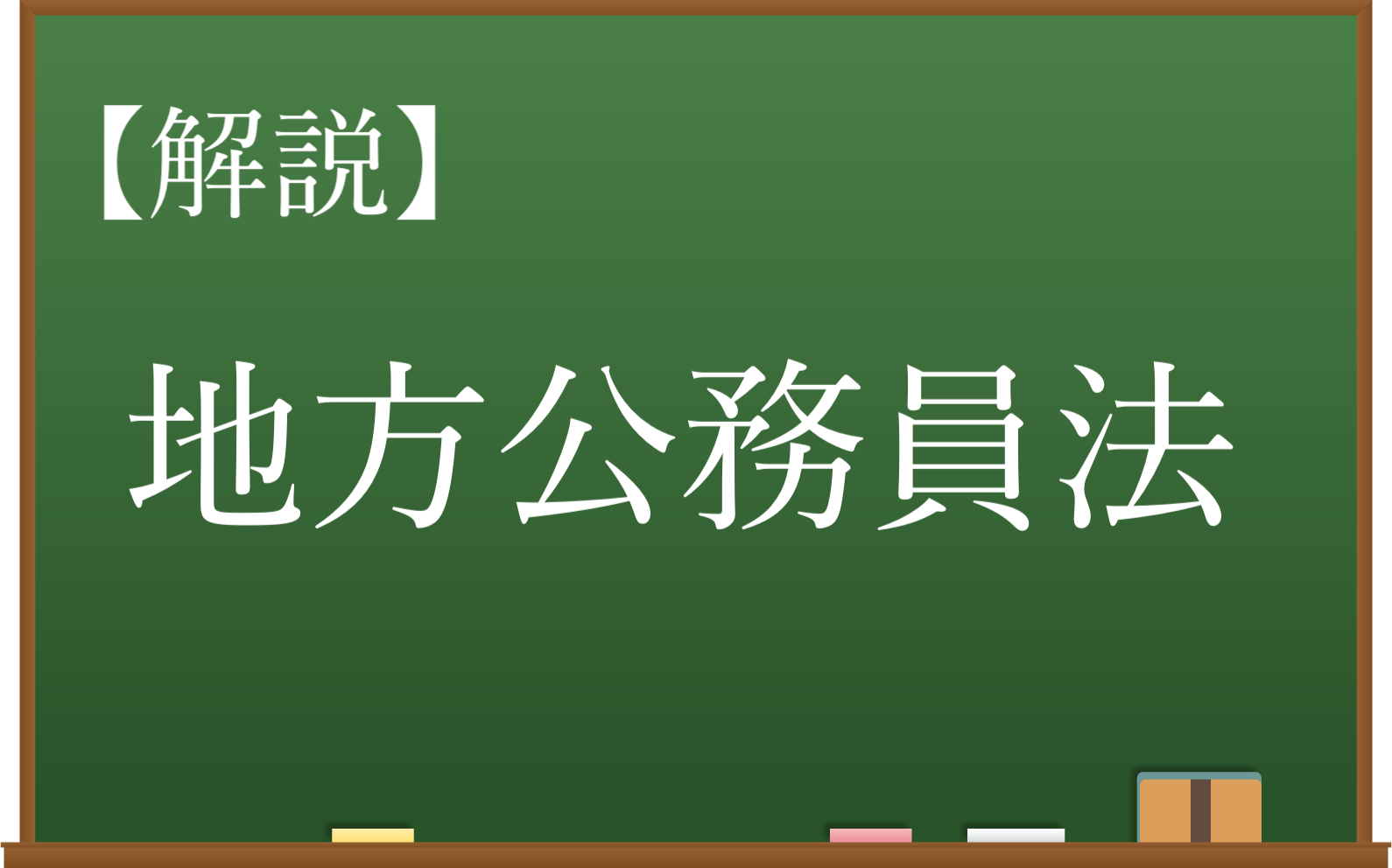
地方公務員法は、地方公務員にとって必ず理解していなければいけない法律の1つです。地方公務員法を理解せずに働いていると、知らず知らずのうちに違法行為を犯している場合があります。
法律に『知らなかった』は通用しません。故意でなくても懲戒処分を受けることがあります。きちんと勉強しない者が悪い、知っていて当然という考え方なのです。
入職したら上司から教えてもらえるんじゃないの?
あなたの配属先の上司が『親切+暇+優秀』であれば教えてくれるかもしれません。しかし、自治体に勤めている方は共感できると思いますが、日々の業務が忙しくてそれどころじゃないのが実態です。
このため、自分で学習する必要がありますが、地方公務員法の条文だけを読んでも、恐らく全く頭に入らないと思います。
そこで、各条文に簡単な情報を添えて、少しでもわかりやすく地方公務員法を解説していきますので、ぜひご覧ください。
法律を使いこなす職員は絶対に伸びる!
目次
- 第一章 総則(第一条ー第五条)
- 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
- 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
- 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
- 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
- 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
- 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
- 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
- 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
- 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
- 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
- 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
- 第二款 公務災害補償(第四十五条)
- 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
- 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
- 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
- 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
- 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
- 附則
第一章 総則(第一条ー第五条)
第一条(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
第一条は、地方公務員法を制定する目的について書かれています。
法律、条例、規則等を読むときには『目的・趣旨・定義』をはじめに確認するクセをつけてほしい。『この法律は、こんな目的でこんな趣旨が書かれているんだ!』という大筋がわかるだけでも、理解度が格段に変わります。また、定義がわからないと、誤って解釈する可能性が高くなります。
第二条(この法律の効力)
(この法律の効力)
第二条 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体のの定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
第二条は地方公務員法の効力について書かれています。
ここで書かれている効力は『地方公務員に関する条例や規則に書かれている中身が、地方公務員法に抵触する場合は、地方公務員の規定が優先されるよ』ということです。
このため、地方公務員に関する条例や規則を制定するときは、地方公務員法に矛盾しないようにしなければいけません。矛盾しないようにするためには、地方公務員法を熟知している必要があります。
第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
第三条は、地方公務員が一般職と特別職について書かれています。
第2項において、一般職は特別職以外の全ての職と書かれていますので、どんな特別職があるのかを簡単に説明します。
特別職が書かれているのは第3項です。
第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
第四条は、地方公務員法の適用を受ける地方公務員について書かれています。原則一般職に対してのみ適用し、特別の定めがある場合以外の場合は、特別職には効力が及ばないことを定めています。
ただし、特別職が一般職を兼ねる場合は、全面的に地方公務員法の適用を受けます。
会計年度任用職員は一般職!
第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
2 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
第五条は人事委員会、公平委員会、職員に関する条例の制定について書かれています。
この条文のポイントとしては、人事委員会が議会において意見を聞く必要があるのに対し、公平委員会についてはそのような規定はないところです。
人事委員会と公平委員会は、人口の多少で分けられた区分ではありますが、権限の有無に関しては、まるっきり異なる組織なのです。